みなさま、こんにちは。
BEYONDO京都四条店トレーナの太田です。

疲れやすい、眠れない、イライラしやすい、頭痛や肩こりが続く、胃腸の調子が悪い。
このような「なんとなく不調」に悩まされている女性の方おられるのではないでしょうか。
厚生労働省の調査によると、成人女性の約60%が自律神経の乱れによる症状を経験しており、特に20-40代の働く女性において、ストレス、不規則な生活、栄養バランスの乱れによる自律神経失調症が深刻化しています。
自律神経は、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)の2つから構成され、心拍数、血圧、消化機能、体温調節、ホルモン分泌など、生命維持に必要な機能を自動的に調節しています。
現代社会では慢性的なストレス、不規則な生活リズム、栄養不足により、この絶妙なバランスが崩れやすくなっています。
しかし、適切な食事とトレーニング習慣により、自律神経のバランスを効果的に整えることができます。
栄養素の最適化、規則正しい食事リズム、自律神経に働きかける運動により、心身の不調を根本から改善し、質の高い日常生活を取り戻すことが可能です。
この記事をご覧いただいている方へ。
この記事をご覧いただいている皆さまは、健康面に気を使い、食生活や運動習慣の見直し、フィットネスジムに通われている。もしくは、入会等をご検討されている健康意識の高い方々ではないでしょうか?
実際に、厚生労働省が、健康づくりのための身体活動基準・指針を作成し、生活習慣病予防のための運動を推進しています。
また、日本政策金融公庫が発表した消費者動向調査(令和3年7月)では、運動面や食に関する志向で、“健康志向”の方が多く年々と増加しています。
より皆様が、健康的で充実した人生を歩めるよう、誠意を込めて記事を執筆いたしましたので、どうか最後までご覧ください。
<その他資料>
※スポーツ庁の資料(新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健康状態等に関する調査研究(令和2年度))では、コロナ終息後のパーソナルトレーニングジムの利用者数は急増中。
※経済産業省の『特定サービス産業動態統計速報』の結果でも、フィットネスジム並びに、パーソナルジム利用者は数多くいらっしゃいます。
【PR】BEYOND

BEYONDは全国150店舗以上を展開する、BEST GYM AWARD受賞のパーソナルジム。美ボディコンテストでの入賞者や資格をもつ、プロのパーソナルトレーナーのみが揃っております。
過度な食事制限やトレーニングなく、ライフスタイルに合わせて無理なく継続できます。
コースは大きく以下3つにわかれているため、目的に合ったトレーニングを選択可能です。
| 料金(税込) ※最小プランの場合 | 内容 | おすすめ | |
| ライフプランニングコース | 月々18,500~ ※323,664円 | パーソナルトレーニング 食事管理 サプリメント | 目標がある方向け |
| 回数券コース | 月々4,700円~ ※102,300円 | パーソナルトレーニング ストレッチ | 継続したい方向け |
※当社指定の信販会社を利用した際の分割料金となります。・10回券96,800円の場合:分割回数:24回/支払い期間:24ヶ月/手数料率:年利7.96%/支払い総額:115,850円
特に回数券コースの月々4,800円~は、業界内でも最安値級で良心的です。
BEYONDが気になる方は、まず無料体験トレーニングを活用してみてください。
\今なら入会金50,000円が無料/
自律神経の科学的メカニズム:バランス調節の仕組み

効果的な自律神経調整のためには、その生理学的メカニズムの理解が不可欠です。
交感神経と副交感神経の役割分担
交感神経の機能は、「闘争・逃走反応」を司り、ストレス状況や活動時に優位になります。
心拍数増加、血圧上昇、呼吸促進、血糖値上昇、消化機能抑制などの反応を引き起こし、身体を活動状態に準備します。現代社会では慢性的なストレスにより、交感神経が過度に優位になりがちです。
副交感神経の機能は、「休息・消化反応」を司り、リラックス時や睡眠時に優位になります。心拍数低下、血圧低下、呼吸深化、消化機能促進、免疫機能向上などの反応を引き起こし、身体を回復・修復状態に導きます。
現代人は副交感神経の活動が不足しがちです。
自律神経バランスの重要性として、健康な状態では状況に応じて交感神経と副交感神経が適切に切り替わります。日中は交感神経優位で活動し、夕方から夜にかけて副交感神経優位に移行することで、質の高い睡眠と翌日の活力を確保できます。
自律神経に影響を与える要因
栄養状態の影響として、特定の栄養素が自律神経の機能に直接的に影響します。ビタミンB群は神経伝達物質の合成に必要で、不足すると神経機能が低下します。マグネシウムは神経の興奮を抑制し、カルシウムは神経伝達を促進します。これらのミネラルバランスが自律神経の安定性を左右します。
血糖値の変動が自律神経に大きな影響を与えます。急激な血糖値上昇は交感神経を刺激し、その後の急降下は副腎疲労を引き起こします。安定した血糖値維持により、自律神経のバランスを保つことができます。
腸内環境と自律神経の関係も重要です。腸は「第二の脳」と呼ばれ、迷走神経を通じて脳と密接に連携しています。腸内細菌の状態が自律神経のバランスに直接影響し、善玉菌の増加により副交感神経の活動が促進されます。
運動が自律神経に与える効果
有酸素運動の効果として、適度な有酸素運動は副交感神経の活動を促進し、心拍変動性を改善します。運動により分泌されるエンドルフィンやセロトニンが、自律神経のバランス調整に重要な役割を果たします。
筋力トレーニングの影響として、適切な強度の筋トレは交感神経を一時的に活性化した後、運動後に副交感神経優位の状態を作り出します。この切り替えにより、自律神経の調整能力が向上します。
ヨガ・ストレッチの効果として、深い呼吸と緩やかな動作により、直接的に副交感神経を刺激します。特に横隔膜呼吸は迷走神経を刺激し、リラクゼーション反応を促進します。
\BEYONDで体験してみる/
自律神経を整える食事法

自律神経のバランスを整えるための、科学的根拠に基づいた食事戦略を詳しく解説します。
神経機能をサポートする栄養素
ビタミンB群の重要性として、神経伝達物質の合成と神経細胞の維持に不可欠です。ビタミンB1(チアミン)は神経細胞のエネルギー代謝に必要で、玄米、豚肉、大豆製品に豊富に含まれます。ビタミンB6はセロトニンやGABAの合成に関与し、バナナ、鶏胸肉、マグロに多く含まれます。ビタミンB12は神経細胞の修復に重要で、レバー、魚類、卵に含まれます。
マグネシウムの神経安定効果により、神経の興奮を抑制し、リラクゼーションを促進します。1日の推奨摂取量は成人女性で270-290mgで、アーモンド、ほうれん草、アボカド、ダークチョコレートに豊富に含まれます。マグネシウム不足は不安、イライラ、不眠の原因となります。
オメガ3脂肪酸の抗炎症効果により、神経炎症を抑制し、自律神経の安定化に寄与します。EPA・DHAは魚油に豊富で、サバ、イワシ、サーモンから摂取できます。α-リノレン酸は植物性オメガ3で、亜麻仁油、えごま油、くるみに含まれます。1日1-2gの摂取が推奨されます。
トリプトファンとセロトニン合成により、副交感神経の活動を促進します。トリプトファンは必須アミノ酸で、セロトニンの前駆体です。鶏肉、卵、チーズ、バナナ、ナッツ類に含まれ、炭水化物と一緒に摂取することで脳への取り込みが促進されます。
血糖値安定化のための食事戦略
低GI食品の活用により、血糖値の急激な変動を防ぎ、自律神経の安定化を図ります。
玄米、全粒粉パン、オートミール、豆類、野菜類は血糖値を緩やかに上昇させ、持続的なエネルギー供給を実現します。白米や白パンなどの高GI食品は血糖値スパイクを引き起こし、交感神経を過度に刺激します。
食物繊維の重要性として、水溶性食物繊維は糖の吸収を緩やかにし、血糖値の安定化に寄与します。オートミール、りんご、海藻類、こんにゃくに豊富に含まれます。不溶性食物繊維は腸内環境を改善し、間接的に自律神経のバランスを整えます。
食事タイミングの最適化により、体内時計と自律神経のリズムを同調させます。朝食は起床後1時間以内に摂取し、交感神経の適切な活性化を促します。夕食は就寝3時間前までに済ませ、副交感神経優位への移行を妨げないようにします。
間食の戦略的活用により、血糖値の安定維持を図ります。3-4時間おきの軽食により、血糖値の大幅な低下を防ぎます。ナッツ類、ヨーグルト、フルーツなどの栄養価の高い間食を選択し、血糖値スパイクを避けます。
腸内環境改善による自律神経調整
プロバイオティクス食品の摂取により、腸内善玉菌を増加させ、腸脳相関を通じて自律神経を調整します。ヨーグルト、ケフィア、キムチ、味噌、納豆などの発酵食品を毎日摂取することで、腸内フローラのバランスが改善されます。特にラクトバチルス・ヘルベティカスやビフィドバクテリウム・ロンガムは、ストレス軽減効果が報告されています。
プレバイオティクス食品の活用により、善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を供給します。玉ねぎ、にんにく、バナナ、アスパラガス、ごぼうに含まれるイヌリンやフラクトオリゴ糖が、ビフィズス菌の増殖を促進します。
腸粘膜の修復により、リーキーガット症候群を予防し、全身の炎症を抑制します。L-グルタミン(鶏肉、魚類、卵に含有)、亜鉛(牡蠣、レバー、ナッツに含有)、ビタミンD(魚類、卵黄に含有)が腸粘膜の健康維持に重要です。
自律神経調整のための具体的食事プラン
朝食メニュー(7:00-8:00)として、オートミール50gに豆乳200ml、バナナ1本、アーモンド10粒、はちみつ大さじ1を組み合わせます。この組み合わせにより、トリプトファン、マグネシウム、ビタミンB群を効率的に摂取し、1日の自律神経リズムを整えます。
昼食メニュー(12:00-13:00)として、玄米100g、サバの塩焼き1切れ、ほうれん草のごま和え、わかめの味噌汁を組み合わせます。オメガ3脂肪酸、マグネシウム、ビタミンB群をバランスよく摂取し、午後の交感神経活動をサポートします。
夕食メニュー(18:00-19:00)として、鶏胸肉のハーブ焼き100g、蒸し野菜(ブロッコリー、人参、かぼちゃ)、キヌアサラダ、カモミールティーを組み合わせます。トリプトファンとマグネシウムにより、副交感神経優位への移行を促進します。
間食メニューとして、午前中(10:00)にアーモンド10粒とりんご1/2個、午後(15:00)にギリシャヨーグルト100gとベリー類50gを摂取します。血糖値の安定維持と必要栄養素の補給を同時に実現します。
\BEYONDで体験してみる/
自律神経を整えるトレーニング習慣

自律神経のバランスを効果的に整えるための、科学的根拠に基づいた運動プログラムを詳しく解説します。
副交感神経を活性化する運動
ヨガの自律神経調整効果として、深い呼吸と緩やかな動作により、直接的に副交感神経を刺激します。特に「太陽礼拝」のシークエンスは、交感神経と副交感神経の適切な切り替えを促進します。週3回、各30分の実践により、心拍変動性が改善し、ストレス耐性が向上します。
呼吸法エクササイズにより、迷走神経を直接刺激し、副交感神経を活性化します。4-7-8呼吸法(4秒吸気、7秒息止め、8秒呼気)を1日2回、各10セット実施することで、不安軽減と睡眠の質向上が期待できます。腹式呼吸により横隔膜を大きく動かすことで、迷走神経への刺激効果が最大化されます。
ストレッチングの効果として、筋肉の緊張緩和により、身体的ストレスが軽減され、副交感神経が優位になります。特に首、肩、腰部のストレッチは、デスクワークによる筋緊張を解放し、自律神経のバランスを改善します。就寝前の15分間ストレッチにより、睡眠の質が向上します。
瞑想・マインドフルネスにより、心理的ストレスが軽減され、副交感神経が活性化されます。1日10-20分の瞑想実践により、コルチゾール(ストレスホルモン)レベルが低下し、自律神経のバランスが改善されます。初心者は呼吸に意識を向ける基本的な瞑想から始めることが効果的です。
適度な有酸素運動による調整
ウォーキングの最適化として、中強度(最大心拍数の60-70%)で20-30分間のウォーキングが自律神経調整に最も効果的です。朝の時間帯に実施することで、体内時計のリセット効果も得られます。週4-5回の継続により、心拍変動性が改善し、ストレス耐性が向上します。
水中運動の効果として、水圧による全身マッサージ効果と浮力による関節負担軽減により、リラクゼーション効果が高まります。水温32-34度の温水プールでの軽い水中ウォーキングやアクアエクササイズは、副交感神経を優位にし、筋緊張を緩和します。
サイクリングの調整効果として、一定のリズムでのペダリングが自律神経のリズムを整えます。平地での軽めの負荷(会話ができる程度)で30-45分間のサイクリングにより、エンドルフィンの分泌が促進され、自然なリラクゼーション状態が得られます。
筋力トレーニングによる自律神経強化
軽〜中強度の筋トレ効果として、過度な負荷を避けた筋力トレーニングは、自律神経の調整能力を向上させます。最大筋力の60-70%程度の負荷で、各部位8-12回×2-3セットを週2-3回実施することで、交感神経と副交感神経の切り替え能力が改善されます。
体幹トレーニングの重要性として、深層筋の強化により、姿勢改善と呼吸機能向上が実現されます。プランク、デッドバグ、バードドッグなどの体幹エクササイズにより、横隔膜の機能が改善され、自然な腹式呼吸が促進されます。
機能的筋力トレーニングとして、日常動作を模した複合的な動きにより、全身の協調性が向上します。スクワット、ランジ、プッシュアップなどの基本動作を正しいフォームで実施することで、神経筋協調性が改善され、自律神経の安定化に寄与します。
時間帯別トレーニングプログラム
朝のアクティベーション(6:30-7:30)として、軽い有酸素運動と動的ストレッチにより、交感神経を適切に活性化します。10分間のウォーキング、5分間の動的ストレッチ、5分間の呼吸法により、1日の自律神経リズムを整えます。
昼間のエネルギー維持(12:00-13:00)として、短時間の軽い運動により、午後の活動に備えます。階段昇降5分間、デスクでできるストレッチ5分間により、血流改善と集中力向上を図ります。
夕方のメイン運動(17:00-18:30)として、1日のメインとなる運動を実施します。有酸素運動20-30分、筋力トレーニング15-20分、ストレッチ10分の組み合わせにより、適度な疲労感を得て、夜の副交感神経優位への移行を促進します。
就寝前のリラクゼーション(21:00-21:30)として、副交感神経を優位にする運動を実施します。ヨガのリストラティブポーズ、軽いストレッチ、呼吸法、瞑想により、質の高い睡眠への準備を整えます。
| 時間帯 | 運動内容 | 実施時間 | 自律神経への効果 | 期待される効果 |
|---|---|---|---|---|
| 朝(6:30-7:30) | 軽い有酸素運動+動的ストレッチ | 20分 | 交感神経適切な活性化 | 覚醒促進、1日のリズム確立 |
| 昼(12:00-13:00) | 軽い運動+ストレッチ | 10分 | バランス維持 | 午後の集中力向上 |
| 夕方(17:00-18:30) | 有酸素運動+筋トレ | 60分 | 適度な交感神経刺激 | 体力向上、ストレス発散 |
| 夜(21:00-21:30) | ヨガ+瞑想+呼吸法 | 30分 | 副交感神経優位化 | 睡眠の質向上、リラクゼーション |
\BEYONDで体験してみる/
生活習慣の統合的改善

食事とトレーニングに加えて、自律神経のバランスを整えるための包括的なライフスタイル改善を解説します。
睡眠の質向上による自律神経調整
睡眠リズムの最適化により、自律神経の自然なサイクルを回復します。毎日同じ時刻の就寝・起床により、体内時計が安定し、メラトニンとコルチゾールの分泌リズムが正常化されます。理想的な睡眠時間は7-8時間で、23時就寝・6時起床のサイクルが推奨されます。
睡眠環境の整備として、室温18-22度、湿度50-60%、遮光カーテンによる暗闇環境が副交感神経の活性化を促進します。就寝1時間前からのブルーライト遮断により、メラトニン分泌が促進され、自然な眠気が誘発されます。
就寝前ルーティンの確立により、副交感神経優位への移行を習慣化します。入浴(38-40度、15分間)、軽いストレッチ、読書、アロマテラピーなどのリラクゼーション活動により、心身を睡眠モードに切り替えます。
ストレス管理と心理的アプローチ
認知行動療法的アプローチにより、ストレス反応パターンを改善します。ネガティブ思考の認識、現実的な思考への転換、問題解決スキルの向上により、慢性的なストレス状態を軽減できます。日記やマインドフルネス瞑想により、客観的な自己観察能力を向上させます。
時間管理とワークライフバランスの改善により、慢性的なストレス状態を解消します。優先順位の明確化、効率的なタスク管理、適切な休憩時間の確保により、交感神経の過度な活性化を防ぎます。
社会的サポートの活用により、ストレス耐性を向上させます。家族や友人との良好な関係、趣味やコミュニティ活動への参加により、オキシトシン(愛情ホルモン)の分泌が促進され、自律神経のバランスが改善されます。
環境要因の最適化
自然光の活用により、体内時計を調整し、自律神経のリズムを整えます。朝の自然光曝露(15-30分)により、メラトニン分泌が抑制され、覚醒が促進されます。日中の適度な自然光曝露により、夜のメラトニン分泌が促進されます。
室内環境の調整として、適切な温度、湿度、空気質の維持が自律神経の安定に寄与します。観葉植物の配置により、空気質改善とリラクゼーション効果が得られます。アロマテラピー(ラベンダー、カモミール)により、副交感神経の活性化が促進されます。
デジタルデトックスにより、慢性的な交感神経刺激を軽減します。スマートフォンやパソコンの使用時間制限、就寝前のデジタル機器遮断により、自然な自律神経リズムを回復できます。
\BEYONDで体験してみる/
4週間実践プログラム

自律神経を整えるための段階的な実践プログラムを詳しく解説します。
第1週:基礎習慣の確立
食事面の改善として、規則正しい食事時間の確立と血糖値安定化を重視します。朝食を必ず摂取し、3食の時間を固定します。間食にナッツ類やヨーグルトを取り入れ、血糖値の急激な変動を防ぎます。水分摂取量を1日1.5-2Lに増やし、カフェイン摂取を午後3時以降控えます。
運動面の導入として、軽い有酸素運動と基本的なストレッチから始めます。毎日10分間のウォーキング、就寝前10分間のストレッチを実施します。呼吸法エクササイズ(4-7-8呼吸法)を朝晩各5回実施し、副交感神経の活性化を促進します。
生活リズムの調整として、就寝・起床時間を固定し、体内時計の調整を開始します。就寝1時間前からのスマートフォン使用を控え、リラクゼーション活動(読書、入浴、軽いストレッチ)を導入します。
第2週:栄養最適化と運動強化
栄養素の強化として、自律神経調整に重要な栄養素を意識的に摂取します。マグネシウム豊富な食材(アーモンド、ほうれん草、アボカド)、オメガ3脂肪酸豊富な魚類、ビタミンB群豊富な玄米や豆類を毎日の食事に取り入れます。
運動プログラムの拡張として、ウォーキング時間を20分に延長し、週2回の軽い筋力トレーニングを追加します。ヨガや太極拳などの心身統合運動を週1回導入し、副交感神経の活性化を促進します。
ストレス管理の強化として、瞑想やマインドフルネス実践を毎日10分間実施します。ストレス日記をつけ、ストレス要因とその対処法を客観的に分析します。
第3週:統合的アプローチの実践
食事とトレーニングの統合として、運動前後の栄養摂取タイミングを最適化します。運動前2時間にバナナやオートミールなどの軽い炭水化物を摂取し、運動後30分以内にタンパク質を補給します。
運動プログラムの多様化として、有酸素運動、筋力トレーニング、柔軟性向上運動をバランスよく組み合わせます。週4回の運動実施を目標とし、各セッション30-45分間実施します。
睡眠の質向上として、睡眠環境の最適化と就寝前ルーティンの完成を図ります。室温、湿度、遮光の調整により、深い睡眠を促進します。
第4週:習慣の定着と評価
習慣の自動化として、確立した食事・運動・生活習慣を無意識レベルで実践できるよう定着を図ります。習慣トラッカーを活用し、実践率90%以上を目標とします。
効果の評価と調整として、自律神経バランスの改善を多角的に評価します。睡眠の質、ストレス耐性、体調の変化、心拍変動性(可能であれば)を記録し、個人に最適なプログラムへの調整を行います。
長期継続戦略の確立として、4週間で得られた効果を維持・向上させるための長期計画を策定します。季節や生活状況の変化に応じた柔軟な調整方法を習得し、持続可能な健康習慣を確立します。
\BEYONDで体験してみる/
よくある疑問と実践的な解決策

自律神経調整において多くの人が抱く疑問と、科学的根拠に基づいた解決策を解説します。
「効果が実感できるまでの期間」について
効果の現れ方について、自律神経の調整効果は段階的に現れます。1-2週間で睡眠の質改善、2-4週間でストレス耐性向上、4-8週間で全身の体調改善を実感することが一般的です。個人差があるため、焦らず継続することが重要です。
早期改善のサインとして、朝の目覚めの良さ、日中の集中力向上、夜の自然な眠気などが挙げられます。これらの変化は自律神経バランスの改善を示す重要な指標です。
「忙しくて時間が取れない」という課題
最小限の時間投資として、1日20分の運動と食事の工夫により十分な効果を得られます。
朝の呼吸法5分、昼の軽い運動5分、夜のストレッチ10分の組み合わせで、基本的な自律神経調整が可能です。
日常生活への統合により、特別な時間を確保せずに実践できます。通勤時の腹式呼吸、階段利用、デスクでのストレッチなど、既存の活動に自律神経調整要素を組み込むことで効率化を図れます。
「食事制限がつらい」という悩み
制限ではなく最適化として、自律神経調整のための食事改善は、厳格な制限ではなく栄養バランスの最適化です。好きな食べ物を完全に排除するのではなく、摂取タイミングや量を調整することで、ストレスなく改善できます。
段階的な変更により、無理なく食習慣を改善できます。週に1-2品目ずつ健康的な食材を追加し、徐々に食事全体のバランスを改善することで、継続しやすくなります。
\BEYONDで体験してみる/
まとめ:統合的アプローチによる自律神経の最適化

自律神経の乱れは、適切な食事とトレーニング習慣により、効果的に改善できます。栄養素の最適化、規則正しい食事リズム、自律神経に働きかける運動、生活習慣の改善を統合的に実践することで、心身の不調を根本から解決し、質の高い日常生活を実現できます。
重要なのは、完璧を求めず、継続可能な方法を選択することです。神経機能をサポートする栄養素の摂取、血糖値の安定化、腸内環境の改善、適度な運動、ストレス管理、質の高い睡眠により、自律神経の自然なバランスを回復できます。
最も大切なのは、自分の体の声に耳を傾け、無理のない範囲で取り組むことです。4週間の段階的プログラムにより基礎を築き、その後は個人の生活スタイルに合わせて柔軟に調整することで、長期的な健康維持が可能になります。科学的根拠に基づいた確実な方法により、自律神経のバランスを整え、心身ともに健康で充実した毎日を実現しましょう。
\BEYONDで体験してみる/
よくある質問
Q.パーソナルトレーニングはキツいですか?
A.パーソナルトレーニングでは、正しいフォーム(姿勢)で負荷を意識してトレーニングするため、自己流のトレーニングよりも「キツい」と感じるかもしれませんが、それはトレーニングの効果を得られている証です。
個人に合った強度のトレーニングをご提供させていただきます。
Q.バーベルやマシンなどに危険はありませんか?
A.バーベルやマシンを利用したトレーニングは、正しいフォームで適切な負荷をかけることで、自重トレーニングよりも効率的なトレーニングが可能です。その分、適切な知識や技術がなければ、やはり危険な部分はあります。
BEYONDジムではトレーニングのプロが危険がないようサポートさせていただきます。
Q.年齢制限はありますか?
A.パーソナルトレーニングに年齢制限はありません。30~40代の利用者が多いイメージがあるかもしれませんが、実際に始めると「もっと早く始めておけば良かった」と感じる人は多いそうです。50~60代になってくると、五十肩や腰痛などの悩みも増えてきます。
Q.女性でも大丈夫でしょうか?ムキムキにはなりたくないですし、お肌も綺麗に保ちたいのですが。
A.多くの女性にこれまでにもBEYONDでダイエットを体験いただました。
目標に合わせてトレーニングメニューを決定しますので、必要な筋肉をつけ綺麗に痩せるためのトレーニングをご提供いたします。
食事管理させてもらうことで、お肌がより綺麗になったとの声も多くあります。
トレーニングによりホルモンの分泌がよくなり、代謝も上がりますので、肌のターンオーバーもしやすくなり、美容効果も期待できます。
Q.パーソナルトレーニングはキツいですか?
A.パーソナルトレーニングでは、正しいフォーム(姿勢)で負荷を意識してトレーニングするため、自己流のトレーニングよりも「キツい」と感じるかもしれませんが、それはトレーニングの効果を得られている証です。
個人に合った強度のトレーニングをご提供させていただきます。
\BEYONDで体験してみる/
BEYOND 京都四条店のお知らせ
| BEYOND京都四条店 トレーナー紹介!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 日吉陸(店長) | 山村聡 | 松田武 | 田淵龍之介 |
| 写真 |  | 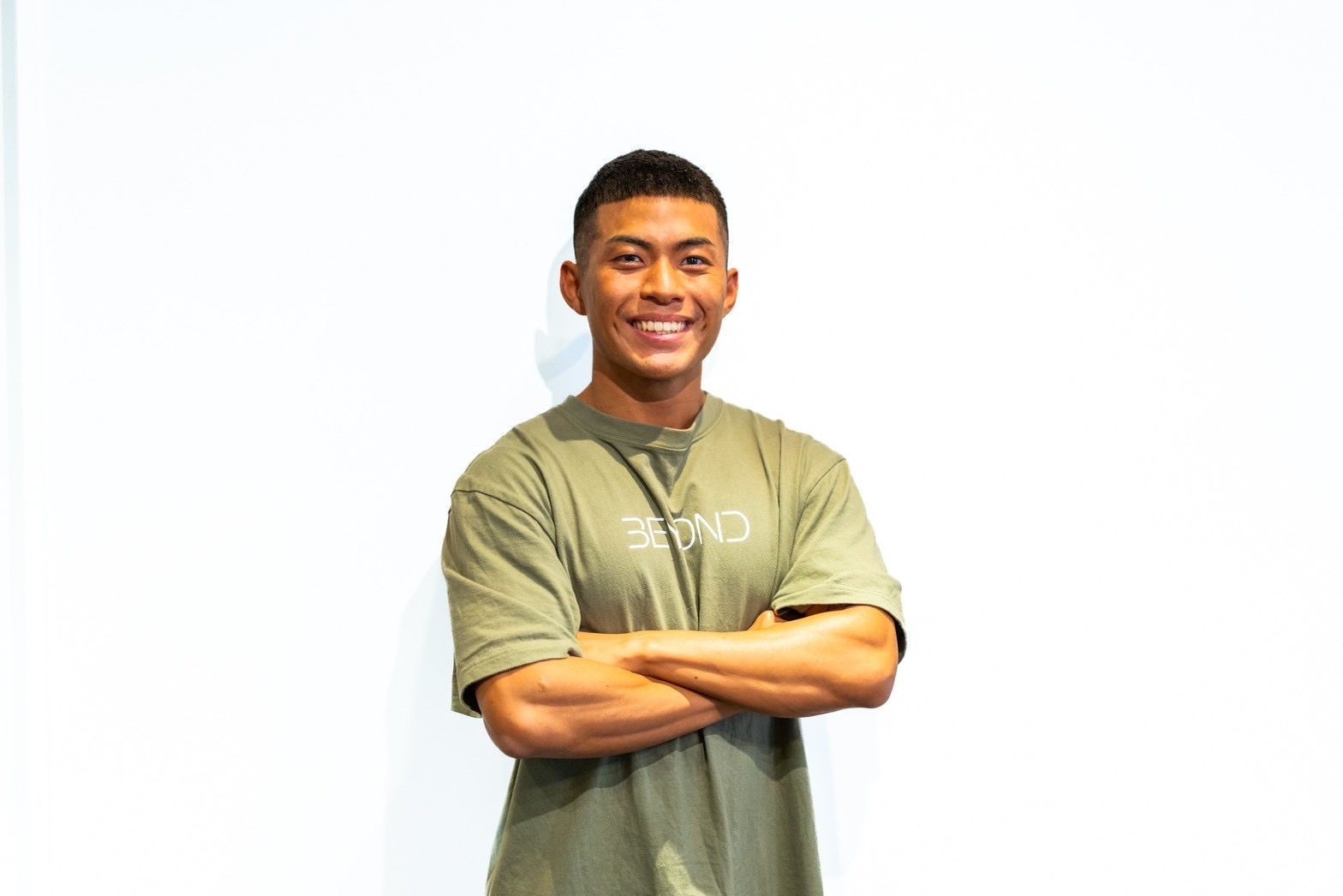 |  |  |
| トレーナー歴 2024年現在 | 4年0ヶ月 | 6年7ヶ月 | 1年0ヶ月 | 0年3ヶ月 |
| スポーツ歴 | 野球、水泳 | 陸上、バスケ | ラグビー、水泳 | ラグビー |
| 好きな食べ物 | ハッシュドポテト | ジャンクフード | お母さんのご飯 | パクチー |
| riku__hiyoshi | so_yamamura | personal_trainer_takeru | taburyu92.fit | |
BEYOND京都四条店の公式Instagramではお得な特典情報や、面白いコンテンツ動画を配信しております。
また、店舗の雰囲気やお客様からのコメント付き写真なども掲載させて頂いております。
私達BEYOND京都四条店は、地域密着型のパーソナルトレーニングジムを目指し、地域飲食店とのコラボ弁当や地域清掃にも取り組んでおり、全国で注目されています!!
会員様が参加頂ける食事セミナーや、女性向けヒップアップスタジオトレーニングなども開催しております。
時には会員様とのお食事会や懇親会も開催しており、会員様どうしで横のつながりもございます。
「モチベーションを上げたい」「トレーニング仲間を作りたい」「新しいトレーニング方法を知りたい」
きっかけは人それぞれです!!どの様なきっかけのお客様でも親身にお話を聞かせて頂き、トレーニングを通じて全力でサポートさせてもらいます!!
YouTubeでは、トレーナーや店舗の雰囲気もわかる動画をアップしておりますので是非チェックして見てください⬇️⬇️
京都市、四条・烏丸エリアでパーソナルジムをお探しの方は、
BEYOND 京都四条店がおすすめです
◆業界屈指のトレーナーによる確実なダイエット・ボディメイク実績
◆3食食べて確実に痩せられる食事指導
◆どんな方でも通いやすい豊富なコース
など魅力がいっぱいのジムです
ぜひ、お問い合わせください!
LINEはこちらから
\BEYONDで体験してみる/
お問い合わせは各店舗ごとにお受けしております。
LINEおよびメールフォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。
LINEまたはお電話でのお問い合わせは店舗一覧よりご希望の店舗へご連絡ください。
| 店舗情報 | |
|---|---|
| 店舗名 | BEYOND 京都四条店 |
| 住所 | 〒600-8091 京都府京都市下京区元悪王子町46-4 やさか長砂ビル2F |
| 電話番号 | 0757441101 |
| 最寄り駅 | 烏丸線四条駅より徒歩3分 阪急京都線烏丸駅より徒歩2分 |

